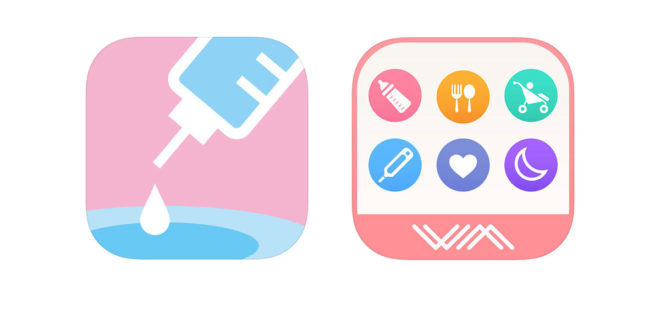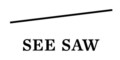体験と知識の両輪で育む主体的な学び
東京から長野へ教育移住した増田です。教育移住して子育てをしている私にとって、「子育てに正解はあるかもしれないし、ないかもしれない」というのが率直な気持ちです。というのは、ここいいなと思った学校に行ったからといってそこに正解があるとは限らないと考えているからです。
その子の特性を見ながら、あっちやこっち、ともに試行錯誤していくプロセスがツラ楽しい(*楽しいけれど時々辛い時もあるから作った造語)時間なのかなと最近は考えています。
私が親になり、試行錯誤しながら多くの先人たちから学んできているのは、リアルな自分の体験から始まる学びの大切さです。
「補助線」としての知識が生む自信
子どもが生まれた時、私は何を食べさせたらいいのか正直分かりませんでした。色々な人が色々なことを言っていて、何を食べさせたらいいのか混乱していました。そこで長い歴史を生きてきた人間が築き上げてきた叡智を頼りにしようと、「食事」について本格的に学び始めました。
ある程度情報を学ぶと、「あ、これはいる、これはいらない」という明確な判断軸を持つことができます。
この学びは、私にとって子育ての判断軸の「補助線」となったのです。
補助線があることで、「これを食べれば元気になる」「これを食べれば頭が良くなる」といった広告に惑わされることなく、自分の判断で実践し、間違っていたら修正していくという循環が生まれました。
重要なのは、「あの人が言ったからこう」という他人軸ではなく、自分なりの答えを導いていくことです。あの人が変わる限り、永遠に自分の自信も変わってしまいます。
もちろん参考にし、プロに聞くということは大切にしたいですが、最終的には自分の頭で考え、判断できる人になる方が安心して生きていられると思って、常に興味を持ったことを少しずつある時間で広げていっています。
段階的に学びを広げていく
食べ物への自信を得た後、私は体調管理について学び始めました。子どもの風邪、皮膚の状態、視力、歯並び、学力…と、だんだん学びの範囲を広げていったのです。
こうして段階的に知識を積み重ねることで、自分なりのブレない軸を持てるようになりました。だからこそ、「この場合どうしたらいいの?」という質問に、表面的には簡単に答えられません。
なぜなら、どういう暮らしをしているか、どういう食生活なのか、どういう生活環境なのかという根本的な部分が深く関わってくるからです。
もちろん、不安になったり心配になることはありますが、最終的に判断は自分に任されています。その時に何を選ぶのがいいのかを自分で考えられる判断の補助線を持つということは、自分の人生を生きることでも大切になってきます。
子育てという機会のおかげで自分だけのためだったら全く興味を持たない分野に興味を持てたことにとても面白さを感じています。
体験と知識の相互作用

現代の多くの学校教育は「まず習ってからやる」というスタイルです。
でも本来の学びは、何かに出会う→「あら、これ何だろう?」と興味を持つ→そこに食いつく→学びたい気持ちが起きる→学んでいく、という流れではないでしょうか。
道でじっと何かを見つめている子どもの姿を見たことがありませんか?たった一つの「何だろう?」という不思議に思う気持ちから広がっていく学びは、その子自身の主体的な学びになります。
もしかしたら、ガムがコンクリートにくっついているのを触ったり観察している子どもに「汚いからもう行くよ」なんて声をかけたことはありませんか?もしかしたら、この子は何か真剣に観察していて、大きな何かを見つけるきっかけを吸収しているかもしれないとみることができたら、少し待つのも楽しくなるのではないでしょうか。
一方で、学んだり知識を持っていなければ気づくこともできない、ということも事実です。本を読んだり、情報に出会ったりするからこそ、新しい体験に気づけることもあります。
大切なのは、どんな情報や体験に出会っても、すべてを自分なりに「検証する」ところから始めることです。受け身ではなく、主体的に向き合うことで、そこからどんどん学びが膨らんでいきます。
この検証から始める学びの方法は、何歳からでも始めることができる方法を知り、最近私自身も地域の人たちや学校も巻き込んで、一緒に日々楽しんでいます。
主体的に始める子どもを育てる
私たちが目指したいのは、「何したらいいの?」「遊びどうしたらいいの?」と常に指示を求める子どもではなく、「こういう遊びがしたい」と自分で勝手に始めてしまうような子どもを育てることではないでしょうか。
体の感覚を大切にし、動物的本能を信じながらも、同時に知識という補助線を持つ。その両方のアプローチを使い分けられる柔軟性が、これからの時代にはとても重要になってくるのではないでしょうか。
日本のように識字率が高く、学校に通える子どもたちの比率が高い環境だからこそ、この両輪の学びを実践していく価値があると思います。
子どもと一緒にゆっくり歩きながら、「これなんだろう?」という好奇心を一緒に育んでいけたら、きっと親も子も、それぞれの自信を育んでいけるのではないでしょうか。
学生時代の海外経験を経て、万博での南米パビリオン勤務、ジンバブエ大使館勤務を経験。その後、12年以上にわたり人材育成の研修イベント運営・営業に携わる。出産を機にシュタイナー教育に出会う。より良い環境を求めて東京から長野県へ移住。現在は「これからの時代の生きる力とは?」をテーマに、次世代の子どもたちの自由な学びと生きる力を育む環境づくりに注力。