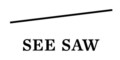終戦から80年、夏に読みたい「戦争と平和」を考える本
季節の本から考える「戦争と平和」
毎日暑い日が続きますね。
夏といえば、毎年手に取るジャンルの本があります。
それは戦争に関する本です。
筆者の祖父(大正末生まれ)は南方からの帰還兵でした。
数年前に亡くなりましたが、孫にとっては、時折厳しくも温厚で、笑顔の印象の強い祖父でした。
ですが、何気ない会話の中で急に「自分が子や孫に囲まれているのは申し訳ない」と言い、悲しそうな表情をすることがありました。戦友は、恋も結婚もせず亡くなっていったのに、自分だけ長生きしてしまったと、罪悪感を感じていたようでした。
終戦記念日が近づき、テレビで戦争の特集が組まれると、番組を見ながら泣く姿も見たことがありました。
そんな祖父の姿を思い返すと、「戦争は、生き残った人のことも、一生苦しめるもの」と強く感じます。
終戦から80年、改めて読むべき本
今年は80年目の終戦記念日です。
夏休みのレジャーも楽しみつつ、読書を通じて戦争と平和を考えてみませんか。
【本の紹介①】シュロモ・ヴェネチア『私はガス室の「特殊任務」をしていた』(河出文庫)
筆者のシュロモさんは、1923年生まれのユダヤ人。アウシュヴィッツに強制収容されますが、そこで「特殊任務部隊」に配属されました。
その任務とは、「仲間のユダヤ人の遺体を焼却処理する」という、なんともつらい内容でした。
しかし、命令ですから、拒否したら自分も罰せられてしまいます。
筆者であるシュロモさんは、その当時のことをこう回想します。
…どこにも出口がなかったんです。みんなそうだった。それに、頭が働かず、何が起きているかなど考えられなかった……みんなロボットになっていた。慣れるより他に方法がなかったんです。
…1、2週間すると、結局慣れてしまいました。全てに慣れました。(中略)最初の10日か20日ぐらい、罪の大きさに絶えず打ちのめされていましたが、それから思考が止まってしまった。
戦後、長らく自分のしたことがうしろめたく、周囲に言えなかったというシュロモさんですが、勇気を出して1992年から証言活動を開始したそうです。
本書には、その当時に起こっていたことが、実際にその目で見てきたシュロモさんにしか書けない克明さで描写されています。
【本の紹介②】小林エリカ『女の子たち風船爆弾をつくる』(文藝春秋)
昨年出版されて話題になったので、お読みになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。イラストレーターでもある著者・小林エリカさんによる愛らしい表紙が印象的な一冊です。
跡見学園や雙葉学園といった女学校に残る資料や、当時を知る元・女学生への綿密な取材をもとにした力作(引用元の注の数はなんと248!)。
昭和の初めに生まれた女の子たち(「わたしたち」)が、戦争を経験し、現在まで生きていくなかでの時代の移り変わりを丁寧に描いています。
バラ模様のレースショールと揃いのパラソルに絹の手袋。淡いコバルトにクリーム色を重ねた春の野の裾まわしの着物。この街は、春の装いに身を包んで浮足立つ人たちで賑わっていた。(中略)その日は、わたしたちの陸軍記念日。日露戦争30周年のお祝いだったから。
冒頭で描かれるのは、日露戦争の戦勝記念に浮かれる人々。服装も華やかで、女の子たちは宝塚の話に花を咲かせています。しかし、物語が進むにつれ、「防空演習」「侵攻」「陥落」といった、きな臭い言葉が増えていきます。戦況の悪化に比例するように、人々の心からもゆとりが失われてゆきます。
わたしの母が、わたしの姉が、わたしが、近所の人から無視されている。うちは女ばかりでひとりも出征させていないから。結婚した姉には子どもができないから、あるいは、子どもはいるけれど身体が悪いから。わたしは、男だったらよかった。
歴史は男性視点で描かれることが多いですが、少女たちの目線から描かれる物語は、今まで読んだ戦争文学のどれにも似ておらず、新しい視点を手に入れたような感覚になります。戦争を生き延びた女の子たちはどんなふうに歳を重ねるのか。そしてこの本のタイトルにもなっている「風船爆弾」とは一体なんなのか…。ぜひ、手に取って実際に読んでいただきたいです。
戦争を知る世代が少なくなった今
戦争を知る世代の方が少なくなった現在。私たちは、先人の残した記録や証言、戦争をテーマにした物語を読み続けていくことで、そのバトンをつないでいきましょう!
居場所がないと感じていた少女時代、放課後と休日のほとんどを図書館で過ごした。小学三年生の時、中原中也の詩に出会ったことで生きる希望を見出す。一人でも多くの人に文学の素晴らしさを伝えるため、日々奮闘中。